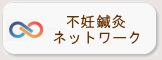三瓶鍼療院 歳時記(ブログ)
福島県白河市の鍼灸院、日常の鍼灸治療の診療日記や、学会参加記、趣味の日記
研究・勉強会
夏季学術講習会
私が所属する社団法人・福島県鍼灸師会では、春・夏・冬、と、年に3回の定期講習会を開催しています。
9月3日(日)は、朝から秋晴れのいい天気(絶好のバイク日和・・・)でしたが、講習会を受講してきました。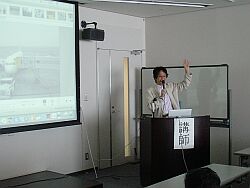 この日の講習会は3部構成。
この日の講習会は3部構成。
まず初め、1部は歯科医学から統合医療を目指す いわき市の中山歯科矯正医院(電話0246-92-4618)の中山孔壹先生です。ご講演の演題は『統合医療が歯科を変える! -歯から全身を診る-』
中山先生のご専門は矯正歯科。しかも非抜歯矯正です。最近増えてきている歯並びの悪い子供から、歯並びの悪くなる原因についてなどからの講義が始まります。
一般的に言われている歯並びの悪くなる原因としては、柔らかいものを食べる食習慣→顎の発育が不十分→歯が綺麗に並ぶスペースが出来ないために、重なって歯が並ぶなどの現象が起きる、と言うものです。
中山先生の研究によると、どうもそれだけでは説明出来ないケースも多くあり、頭蓋骨や口蓋の発育が不十分なために起こりうるケース(鼻呼吸ではなく、種々の原因で口呼吸をしている場合など)が多くあり、先生は専門の矯正歯科だけではなく、カイロプラクティックやオステオパシーなどの理論も深く研究されています。
また先生は、『歯を抜かずに矯正する』という技術や痛みの管理で、経穴に対する銀粒や異種金属の貼り付けなどを行い、見事な成果を上げられています。ご講演の資料として、非抜歯矯正における治療期間中の歯の動きを動画で見させて頂きましたが、おそらく数ヶ月〜年単位での観察期間があったと思われる根気強い治療の成果が目で追って確認出来、大変興味深いものでした(3回も繰り返し見させて頂きました)。 ご講演の終わりには中山先生の歯科医院スタッフ様から会場に大きな花束が届けられました。
ご講演の終わりには中山先生の歯科医院スタッフ様から会場に大きな花束が届けられました。
写真は、代理で贈呈する鍼灸師会会員・青年部副部長の矢吹先生。
貴重なご講演、ありがとうございました。 第2部はお昼休みを挟んだ午後1時から。
第2部はお昼休みを挟んだ午後1時から。
ご講演は『粘膜免疫と歯周病・アレルギーとの関連』と題し、栄養療法コンサルタント・栄養補助食品販売「ウェルライフはちや」代表の蜂屋清美先生です。
『粘膜は皮膚の表面積の200倍の面積を持っており、常にウイルスなどの微生物と接し、粘液で保護されている。生体の免疫の第一歩は粘膜から行われている』から始まり、マクロファージ、Tリンパ球、Bリンパ球、IgA、IgG、IgE抗体などの免疫の関与について話され、『粘膜免疫は血液中の抗体も増加させる』と締めくくられていました。
漠然と、『ヨーグルトは花粉症などのアレルギーに効果がある』とテレビなどで知っていましたが、あらためてそのメカニズムを知ると、これから寒くなってインフルエンザなどの流行する前にこういった免疫の勉強をすることは非常に有意義なことだと思いました。 第3部、今月秋田市で開催される東北鍼灸学会で発表予定の生江先生のリハーサル発表。昨年、郡山市の柴宮団地のすぐ近くに生江鍼灸治療院(福島県郡山市大槻町字原田55-21, 電話024-946-6277)を開業された、鍼灸師会でも若手気鋭の先生の一人。
第3部、今月秋田市で開催される東北鍼灸学会で発表予定の生江先生のリハーサル発表。昨年、郡山市の柴宮団地のすぐ近くに生江鍼灸治療院(福島県郡山市大槻町字原田55-21, 電話024-946-6277)を開業された、鍼灸師会でも若手気鋭の先生の一人。
昨年、日本鍼灸師会が主催する鍼灸臨床指導者講習会を受講され、今年度は初の学会発表となります。
鍼灸師会では、発表する内容や進行についてあらかじめリハーサル発表を行っています。県を代表する発表ですから内容などに不備があってはまずいですし、何よりも学会の発表では発表内容と同じく質疑応答も非常に大事で、会場の参加者からは実に様々な質問が出ます。こういった雰囲気にあらかじめ慣れておくことも非常に大切です。
生江先生の発表演題は、『肌トラブルに対する灸治療』で、頑固なニキビ(挫創)に対する有効な治療法の一つとして、鍼灸治療は非常に有効であると言うもの。発表内容もなかなかのものでした。 今回の東北鍼灸学会では生江先生の初発表のほか、座長役の矢吹先生も初デビューとなります。生江先生のリハーサル発表の際、座長のリハーサルも行いました(矢吹先生は写真右、中央は計時担当の白井先生、写真左は当会・安斎会長)。
今回の東北鍼灸学会では生江先生の初発表のほか、座長役の矢吹先生も初デビューとなります。生江先生のリハーサル発表の際、座長のリハーサルも行いました(矢吹先生は写真右、中央は計時担当の白井先生、写真左は当会・安斎会長)。
以上、この日は3部構成の講演が行われました。
鍼灸師会会員のほか、全日本鍼灸学会会員、また福島盲学校からの多数の先生、学生が参加されました。少々残念に思うのは、郡山市に2つも鍼灸学校があって、その学校からの参加者が合計で3名しかいなかったと言うこと。
学生については、特別にワンコイン(500円、一般参加者は5000円)での参加が出来るように今回は案内しましたし、これからも当分そういった特別参加費で参加出来るように案内をします。
近い将来に国家試験に合格し、晴れて鍼灸師となって鍼灸を一生の業とするなら、今からこういった講習会に積極的に参加した方がよいだろうと、人ごとながら心配致します。
18年度総会+春季学術講習会
4月23日(日)は、午前中に我が福島県鍼灸師会の18年度通常総会と、午後から春季学術講習会が開催されました。
総会では今年度は役員改選があり、これまでの高橋秀行先生(二本松市)から、新しい会長として安斎昌弘先生(二本松市安達町)へ会長職がバトンタッチされました。
以降は午後からの春季学術講習会です。 演題名は『正経・奇経統合理論とその臨床』
演題名は『正経・奇経統合理論とその臨床』
高橋先生は東北の鍼灸師会ではじめて青年部を設立し、長年にわたってご活躍され、4期8年の会長職を勤められました。
私は臨床家としての高橋先生をほとんど知りませんでした。ただ理事会や会合で先生のお話伺うときに奇経治療を実際の臨床に取り入れられ、またその道では知らぬ方がいない山下詢先生に教えを受けたそうで、機会があればぜひご講演を、と考えていました。 会長の講演を拝聴するのは、たぶんほとんどの会員の先生方もはじめてであったと思います。
会長の講演を拝聴するのは、たぶんほとんどの会員の先生方もはじめてであったと思います。
みなさん真剣に講義を聴き、静寂な会場内ではメモ書きのペンの音が時折響いていました。 奇経治療の理論を講義され、その後は会員の中からモデルを募っての実技披露でした。
奇経治療の理論を講義され、その後は会員の中からモデルを募っての実技披露でした。
人体には経絡と言われる目に見えない線路のようなものが存在し、その線路にはたくさんの駅(経穴=つぼ)があります。実際にその線路を走っている列車は『気』であり、鍼灸はその気の動きをコントロールして疾病の治療をします。
気の流れる線路=経絡は、手足の三陰三陽の正経12経脈に任脈・督脈を足した14経脈があり、そのほかに奇経として帯脈や陽維脈など8つがあります。
これら14の経脈と8つの奇経を統合してとらえる高橋先生の治療は、気の動きをわずか数本の刺鍼で統制するという見事なもので、ご自身の40年を超える臨床の中で培ってきたと納得させられました。
『胸の中がすーっとしていくようだ』とか、『刺鍼中にお腹が減ってきた』など、モデルとなった会員の先生の感想から、たった数本と言う少ない刺鍼でも生体は反応することに驚いている様子がうかがえました。
生理的にも侵襲の少ないこのような経絡・奇経治療は、たとえば産科領域(不妊症や逆子など)の治療に最適な治療ではないかと思います。
冬季学術講習会

10月23日には、郡山の郡山市労働福祉会館において私が所属している鍼灸師会の定期学術講習会が開催されました。
この日の講師は、写真の小野直哉先生です。
特別講演
「相補・代替医療と統合医療の現状と展望」
−日本、そして世界−
京都大学大学院医学研究科 小野 直哉先生
小野先生は、明治鍼灸大学を卒業され、京都大学大学院で統合医療の経済効果について特に研究されています。
縁あってはるばる福島県までお越しになり、現在の世界の代替医療の現状をお話しくださいました。
代替医療の中でも、特に鍼灸は世界で発表されている文献数も飛び抜けて多く、健保適応となっている漢方薬などは足元にも及ばないそうです。
米国、またヨーロッパ各国でも代替医療を国民医療の中に取り入れて、今後伸びていく国民医療費を効率的に運用するような動きが見え始めている、とのことでした。