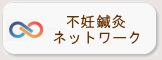三瓶鍼療院 歳時記(ブログ)
福島県白河市の鍼灸院、日常の鍼灸治療の診療日記や、学会参加記、趣味の日記
不妊症
妊娠すると言うこと・鍼灸の不妊治療について(2)
妊娠しやすい体質にすること、妊孕性の向上とは、一回ごとの治療の地道な積み重ねによる体質改善であると、前回書きました。
しもやけが出来るような冷え(血行不良=末梢血管の通りの悪さ)があれば、FSHやLHなどのホルモンの通路(血行)も良くないでしょうし、子宮内膜などの黄体期における反応も悪いことでしょう。
また卵巣内で卵胞が成熟して値が増すエストロゲン・E2のフィードバック作用も血行不良があれば弱いかも知れません。せっかく卵胞が成熟してきても、LHサージが弱かったり、子宮頚管粘液の分泌が少ないとか、子宮内膜があまり厚くならいとか、そんな影響も考えられます。
鍼灸の効果はホルモンの通路を確保である血行を良くすることだけではなく、免疫を改善することも効果の一つに挙げられます。
自然妊娠を助ける鍼灸治療は、たとえば病院で行われるタイミング指導や、クロミッドなどの排卵誘発剤を使った排卵誘発周期+タイミング指導から、人工授精、体外受精を行などの高度生殖医療を行う周期まで、病院の治療と合わせて行うことも出来ます。
血行を良くしたり、また全身や骨盤内の免疫の改善を目指す鍼灸は、単独でも妊孕性を向上させますし、すでに病院での治療を行われていらっしゃる方にはその治療を邪魔することなく、有効な補助治療としておすすめできます。
妊娠すると言うこと・鍼灸の不妊治療について(1)
良く電話やメールで、
『いつ(周期中のどのタイミングで)治療をすると、効果が出やすいのですか?』という質問をされます。
hCGなどの注射のように、打って36時間すると排卵するとか、そのタイミングに合わせて治療をすると妊娠しやすいんじゃないか、と、一回ごとの成功率を鍼灸に求めていらっしゃる方が、なかなか多いようです。
妊娠とは、避妊せず正常な性生活を持っていれば、たとえば20代のカップルならば数ヶ月間、長くとも1年で妊娠されるのが普通です。
妊娠しないのには何らかの原因が存在するのですが、専門医の検査でそれが分かる場合もありますが、レーなところがあるとしても確定的なところが分からない場合が多いようです。
排卵障害、黄体機能不全、高プロラクチン血症、卵巣チョコレート嚢種、子宮内膜症、、、卵管の通りが悪い、、(軽度の)乏精子症など、基礎体温をみたり、ホルモン検査などをすればたいてい何かしら引っかかるものです。
はっきりした原因が分からない不妊の方の場合は、たいてい上記の複数の原因が周期ごとに災いしたり、ただ単にタイミングの時期の問題、回数の不足などがあるのではないかと思います。
つまり機能性(はっきりした原因のない、なんとなく体の状態が悪い)不妊が多い中で、鍼灸による不妊治療は、一回ごとの宝くじを買うようなものはなく、地道な一回ごとの治療効果の積み重ねによる体質改善から効果をめざすものだと私は思っております。
体外受精のアシストとしての鍼灸(特に着床改善)
原発事故から早7ヶ月が過ぎました。
震災の直前に2名の方が胚移植をして、無事着床、と言うところであの忌まわしい大惨事が起きてしまいました。
ご両名とも、あの大変な時期を切り抜けられ、妊娠20週を迎えて当院の不妊治療は無事終了。
今月から、今度は安産に向けた治療に入りました。
体外受精の成功率を上げるため、鍼灸を行うという方が大変多くなってきています。
一つは、何度か採卵され、卵子の状態などが思わしくなかった方や、数度移植しても妊娠に至らなかった方などが、鍼灸をのぞまれるほとんどのケースのようです。
卵子の状態を改善するためには、半年以上に渡る治療が必要ですし、これはなかなか大変です。
京都の中村先生が卵子のエイジングに詳しく、生物科学レベルで実に様々なことを教えてくれます。いずれそのようなお話しをしたいと思いますが、今日は着床について書いてみたいと思います。
形態、分割速度とも申し分のないグレードの良い胚盤胞を数度移植しても妊娠できない、と言うような現象から着床していない、着床できない、という着床不全という概念が最近言われるようになりました。
着床とは、黄体因子、子宮内膜因子、胚因子がいずれもが譲れない因子となり、それぞれが時間的に複雑に関係し合っています。
ハッチングした胚は子宮内膜上皮に乗って接着が起こります。その際にトロフィニンとインテグリンという物質が接着剤の役割をすると言うことです。
インテグリンがよりよい働きをするためには、炎症反応などによって出現するケモカインの働きが必要とのことです。
鍼灸がケモカインの発現に関与している可能性は、以前の記事で書きましたが、おそらくそのような働きも一つの要因なのではないかと思います。
【ケモカインとプロスタグランディン】
http://www.sanpei89in.com/diary/diary.cgi?no=801
参考文献:産科と婦人科 『着床不全の改善を目指して』2003 No.10 診断と治療社