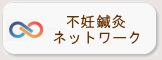三瓶鍼療院 歳時記(ブログ)
福島県白河市の鍼灸院、日常の鍼灸治療の診療日記や、学会参加記、趣味の日記
不妊症
卵管の働きと不妊症(1)
良好な卵胞ができていて、排卵もある。子宮の内膜の厚さも十分で、着床する環境が良好である、というのが、一般的な妊娠の条件であるかと思います。
当院でも卵巣の働きを改善し、子宮の血行の改善を目的にした治療を不妊治療の柱にしています。
またここ数ヶ月前よりは卵管の機能の向上についてもいろいろ考えて治療をしています。
患者さんによって治療の内容・方法ももちろん異なるわけですが、最近は卵管の働きの改善を意識して治療点を変えたり、自宅ですすめているお灸のツボを処方しています。
卵管の働きがヒトの妊娠には大きな役割を果たしていて、ヒトなどの高等哺乳動物以外は体外受精の場合胚盤胞移植でなければ妊娠出来ないと言われています。
受精直後の四分割胚を移植して妊娠・出産するのは人間くらいだろうと言われています。
これはヒトの妊娠に関して卵管が大きな役割を果たしている事実を示唆しているものと考えられます。
二足歩行がゆえのことなのか、進化の過程の事であるのかはもちろん分かりませんが、人間だけが持つ妊娠の不思議さと言えるでしょう。
卵管の働きが悪いことによる女性不妊では、卵管閉塞とピックアップ障害が考えれています。後に書きますが、これ以外にも培養室の働きを持つ卵管では、卵子の輸送以外にも不妊となり得る原因がありそうだと考えています。
不妊症のルーチンな検査では、一般的には種々のホルモン値の検査や、卵管の通過性の検査、卵胞の発育期には発育卵胞、成熟卵胞があるかどうかなどの観察、排卵しているかどうかなどの検査、子宮内膜の厚さの観察などがあります。
( 大事な検査ではフーナー(ヒューナー)テストと言って、性行為後に子宮内に精子が到達しているかどうかをみる検査があります)
卵管の場合は通過性があれば、とりあえずは合格と言うことになります。
妊娠の第一の関門は、卵子と精子が出会えることだと思います。もちろん男性側の因子もあって、この段階でも女性だけの問題ではありません。
卵管閉塞は、高度なものは鍼灸治療ではどうにもなるものではなく、体外受精などのART(高度生殖医療)の絶対適応になるので省きます。
ピックアップ障害について少々思うことを書いてみます。
卵巣にあった発育卵胞が排卵し、卵管に取り込まれる際には卵子が卵管の入り口を目指して泳ぐのではなく、卵管が卵巣の表面を包み込むように移動して卵管を取り込むことが知られています。
取り込まれた卵子は、子宮までの移動する間に卵管膨大部で精子と出会って受精するわけですが、ここまでの卵巣から排卵された卵子を取り込む現象をピックアップと呼び、原因不明の不妊の多くはこれが原因であろうと加藤レディスクリニック院長の加藤修先生はその著書の中で述べています。
ピックアップ障害の原因としては、子宮内膜症の繰り返しの発症と炎症による癒着(多くは卵管との癒着を伴うでしょう)により、卵管が自由に動けない、また卵管采がよく働かないことを挙げています。
丁度ゲームセンターにあるUFOキャッチャーを想像して頂くとわかり安と思いますが、ロボットアームが途中で引っかかっていてはアイテムを取ることはできません。
これが卵子をピックアップできにくい卵管であろうと考えます。
また卵管の先、卵子を取り込む部分は卵管采と呼ばれる部分ですが、良く喩えられる言い方では『イソギンチャクの触手のよう』と言われるようです。
不妊症の治療で訪れる患者さんに接していると、過去に生理痛がひどかった、と言う方が大変多いように思います。これは子宮内膜症の存在を示唆しているのかも知れません。
生理痛を強く訴えている(過去に訴えていた)患者さんの腹部は部分的にとても固く、東洋医学で言う『腹部瘀血(おけつ)』と呼ばれる状態に良く遭遇します。
固いお腹であれば、腹腔内の圧力も高いでしょうし、そんな状態では癒着があってもなくても卵管は運動しにくいでしょう。
ちょうど、重い布団を何枚もかけられると寝返りも打ちにくい状態、と表現すればわかりやすいかと思います。
鍼灸治療を続けていると、ひどい生理痛でも良く改善しますし、腹部?血もまた改善し柔らかいお腹になっていきます。
ひどい癒着でなければ、鍼灸は腹部の血行を改善し、腹圧を減少させるなど卵管の軽度のピックアップ障害に対して良い治療になるのでは?と思います。
なお、以上の内容については非常に独善的であって、医学的根拠には乏しいものです。
間違っても引用したりしないようにお願い致します。
当院は実験的な施設も環境もなく、患者さんや動物を使った生体実験は行っておりませんし、日々日常の診療中に思いついたこと、疑問に思ったことを書き連ねているに過ぎません。
卵管の働きについては、卵子の運搬や受精後の培養もあります。
これについても鍼灸は有用だと思いますので、後に書きたいと思います。
不妊治療について思うこと
毎日不妊症の患者さんの治療を行い、感じることがあります。
今は書籍も良いものが多くあり、またネットの利用で気軽に最新治療の現場をのぞけるようになりました。
大変便利で喜ばしいことなのでしょうけども、どうかすると情報の一人歩きを感じることもあります。
難解と思えるホルモンの名前や正常値、異常であった場合考えられる疾患名や、それについて使われる薬剤。周期によって使い分けられる薬剤や注射など、調べる気になればすぐ調べられるような環境です。
患者さんもいろいろご自身について調べることもあるでしょう。
鍼灸治療は、あらゆる治療を行っても良い結果が出なかった方がいらっしゃるような印象があります。
以前は採卵の段階でよい卵胞がたくさん採れたのに・・・とか、受精後は杯盤胞まで良く育ったのに、とおっしゃる患者さんが多くおられます。
歳を重ねれば条件が悪くなるので、もちろんそう言ったこともあるでしょう。また治療歴が長くなれば薬剤による体への負担が積み重なるので、そうなっていくのかと思います。
日々が経過してゆくとまた焦ることもあると思いますが、思い切ってすべての治療を中断して体を休ませることも必要な時があるのではないかと思います。もちろん鍼灸も含めて。
しばらくのんびり不妊であることを忘れて、ごく普通に生活され、また気になれば治療に復帰されるとよいと思います。
今まで治療を行ってきたケースでは、クロミッドなどによる卵巣刺激を行いながらタイミング療法を行ってきた方がしばらく治療を中断し、その間鍼灸を続け、またクロミッドなどによる治療を再開したら、その最初の周期で妊娠した、とう方が多くいらっしゃいます。
長くなる道のりかも知れません。
だからときどき休息も必要だと思います。
『生殖医療のすべて』 山王病院院長 堤 治先生著 を読んで
先日ご紹介させて頂いた加藤レディスクリニック院長の書かれた本とは対照的な、日本ではスタンダードな不妊治療について詳細に、かつわかりやすく書かれた本です。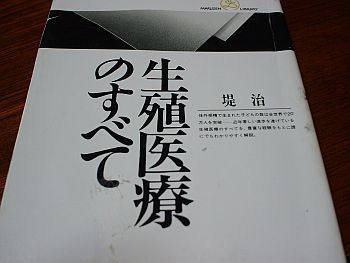
『生殖医療のすべて』
丸善ライブラリー刊 789円
ISBN-9784621052853
内容
第1章 妊娠の成立―生命誕生のしくみ;
第2章 不妊診療の入り口で;
第3章 不妊症の診断と治療;
第4章 体外受精とその応用;
第5章 環境ホルモンと生殖;
第6章 子宮内膜症と不妊;
第7章 内視鏡・腹腔鏡の威力;
第8章 出生前診断・着床前診断;
第9章 生殖医療の問題点;
この本では東大産婦人科学教授であったころからの堤先生の研究テーマである環境ホルモンと生殖や、腹腔鏡による手術について深く書かれています。
また前編の妊娠の成立や診断や治療、体外受精とその応用の話は、生殖や不妊を理解する上で大変わかりやすく書かれています。
特に治療に際して調べられるホルモンの異常や使われる薬剤の意義と注意すべき問題点について効果だけではなく負の部分については、臨床医の立場よりも科学者の目での効能を中立に書かれていると感じました。
これまで普通に行われている不妊治療の問題点を挙げながら、今後さらに高度に進んでいく治療についても触れられています。
当院へは福島県内からの不妊の患者さんから、県境をまたいで栃木県北部(那須塩原市、大田原市、那須町)の方も多くいらっしゃいます。
その方たちの何割かは、西那須野にある国際医療福祉大学のリプロダクションセンターに受診されている方がいらっしゃいます。
現在この本の著者の堤先生は、山王病院の院長をされながら国際医療福祉大学の教授もおつとめになられています。(山王病院の部長クラスは、ほとんど国際医療福祉大学の教授のようです)
国際医療福祉大学・リプロダクションセンターに受診されている方は、一読されてはいかがでしょうか?
また不妊治療を行う鍼灸師のみなさんなども気軽に買える本ですので、ぜひお読みください。
読書の感想を書こうと思いましたが、先に紹介させて頂いた加藤レディスクリニック院長・加藤修著の『不妊治療はつらくない』とあわせ、後日書いてみたいと思います。